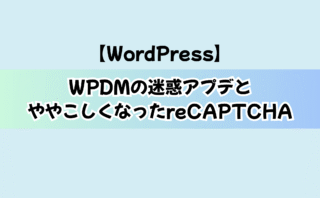第一章:群れに属さない、白き孤高の影
山深く、静寂の中にキジ模様を宿した真っ白な少女、ぼっちゃん。
彼女は兄弟の中でも際立って体が大きく、その存在はどこか謎めいていました。
兄弟たちが連れ立って無邪気に遊んでいるときも、彼女だけはその輪から離れ、独り静かに森の影へと姿を消します。
彼女がどこで、何をしていたのか、知る者は誰もいません。

ただ、兄弟たちが空腹で鳴く頃、彼女はどこからともなく悠然と現れるのです。
みんなと一緒にご飯を食べることはほとんどないのに、その体格は誰よりも立派で、その瞳は鋭い。
それは、彼女が独りで闇に紛れ、誰にも教わらずに狩りの術を身につけていた証でした。
「群れ」ではなく「個」として生きる。彼女は幼いながらに、山で最も優れたハンターだったのでしょう。
第二章:五ヶ月という歳月が、彼女をリーダーにした
生後わずか五ヶ月。本来ならまだ親の愛を一身に受け、甘えて過ごすはずの時期です。
しかし、ぼっちゃんが置かれた環境は過酷でした。
彼女は「ただの子供」でいることを許されなかったのです。
逞しい体格でスプレー行為をして縄張りを主張し、兄弟たちの背後に立って常に周囲を警戒する。
その姿と、頭の模様がまるで「坊ちゃん刈り」のようだったことから、私は彼女を男の子だと信じて疑わず、山時代は「ぼっちゃん」と呼んでいました。
女の子だと判明してからは、後付けで「ボンヌ」という名も贈りましたが、あの頃の彼女は間違いなく、家族を背負う騎士のようでした。
彼女がこれほどまでに強く、臆病なまでに慎重なリーダーシップを持たざるを得なかったのは、そうしなければ自分も、大切な家族も生き残れなかったからです。
親猫の前でだけ、ピンと尻尾を立てて愛おしそうに甘えに行く。
そんな本来の姿を心の奥に封印し、人間に対しては鉄壁の境界線を引くことで、彼女は一度も欠けることなく命を繋いできたのでした。
第三章:山の匂いと、あたたかな決別
私が彼女を山から連れ出したとき、ぼっちゃんのプライドは激しく燃え上がりました。
新しい家での十時間以上に及ぶ籠城、近づく者を拒む鋭い威嚇。

それは、これまで独りで戦ってきた彼女が、自分に課した「守護者」という任務を全うしようとする、孤独で誇り高い抵抗でした。
家に来て二十六日目。初めてのシャンプー。
それは、彼女の体に染み付いた「山の記憶」を洗い流すと同時に、その小さな肩に背負い続けてきた重すぎる荷物を、そっと下ろすための儀式となりました。
第四章:朝の光の中で、取り戻した「本当の自分」
私たちが家族になって、三ヶ月が過ぎる頃。
賢すぎる彼女は、ついに一つの真実を悟ります。
「もう、独りで戦わなくていい。誰かのために、自分を殺さなくてもいいんだ」

今のぼっちゃんは、自由奔放で気高いレディです。
ご飯は自分のペースで楽しみ、気が済めば「ごちそうさま」と手を振って優雅に去る。
日中はかつてのハンターのように、一人の時間を悠々と楽しんでいます。
けれど、朝。私がふと目を覚ますと、すぐそばでぼっちゃんがじっとこちらを見つめていることがあります。
その瞳は、山の頃の鋭さとは違い、どこか確かめるような優しさに満ちています。
「今日もここにいてくれる?」 「私はここで、甘えてもいいんだよね?」 言葉にはなりませんが、彼女は毎朝、私を見つめることで自分の安息を確認しているのかもしれません。
かつて山で戦うために使ったその力は、今では私の腕の中で、一生懸命に愛を伝えるためだけの「もみもみ」に使われています。
夜中に私が席を立っても、戻ってくれば無言でスッ……と腕の中に収まるその姿。
それは「何があっても、私の場所はここだけ」という、彼女が一生をかけて選び取った、究極の信頼の形です。
あの日、孤独なリーダーとして生きる緊張感を脱ぎ捨て、私を信じて身を委ねるという「一番の勇気」を見せてくれた彼女。
ぼっちゃんにとっての本当の猫生は、今、私の腕枕の上で、誰にも邪魔されることなく、穏やかに刻まれているのです。
※Geminiによって真実を元に物語を書いてもらいました。